☕ 昔の喫茶店といえば「角砂糖」
今ではカフェやチェーン店で見ることが少なくなった角砂糖。
でも昭和〜平成初期の喫茶店では、
コーヒーカップのソーサーにトングと角砂糖が2〜3個、
小さなミルクピッチャーと並んで出てくるのが当たり前でした。
なぜ、角砂糖は喫茶店の象徴となったのでしょうか?
🟫 角砂糖が愛された理由
1️⃣ 上品で“特別感”があった
白い陶器のカップと銀のトング、真っ白な角砂糖の組み合わせは、
「お店でしか味わえない特別な時間」 を演出していました。
家ではグラニュー糖や上白糖が一般的だった時代。
角砂糖=喫茶店の非日常感 という図式があったのです。
2️⃣ 砂糖の量が分かりやすい
角砂糖1個は約3〜4g、小さじ1杯分の甘さ。
- 1個 → ほんのり甘い
- 2個 → しっかり甘い
というように甘さの調整が簡単でした。
お客さん自身が好みに合わせて甘さをコントロールできる点も好評だったのです。
3️⃣ “おもてなし”の所作があった
小皿に盛られた角砂糖をトングでつまんでカップに入れる──
その所作自体がちょっと優雅で、喫茶店ならではの演出でした。
“飲む”だけでなく「コーヒーを楽しむ時間」を提供するのが喫茶店。
角砂糖はその雰囲気作りに欠かせないアイテムだったのです。
📉 なぜ今は見なくなったのか?
- 管理やコストの問題
角砂糖の補充や保管が手間だった。 - 衛生面の懸念
盛り付けたまま置くとホコリや湿気が気になるようになった。 - ガムシロップの普及
アイスコーヒー文化とともに、液体のシロップが主流になった。
こうした背景から、徐々に角砂糖は“レトロ”な存在になっていきました。
🌟 今も角砂糖に出会える場所
- 老舗の 純喫茶
- ホテルのティーラウンジ
- ヨーロッパ風のクラシックカフェ
こうした場所では、今も変わらず角砂糖とトングがコーヒーの隣に添えられています。
🎯 まとめ
- 角砂糖は、上品さ・特別感・おもてなしの象徴だった
- 甘さの調整がしやすく、喫茶店らしい所作を生んでいた
- 今では少なくなったが、純喫茶やクラシックカフェでまだ出会える
✅ コーヒーを飲むとき、たまには角砂糖を使ってみませんか?
トングでそっと角砂糖をつまむ所作だけで、ちょっとした“昭和の喫茶店気分”が味わえます。
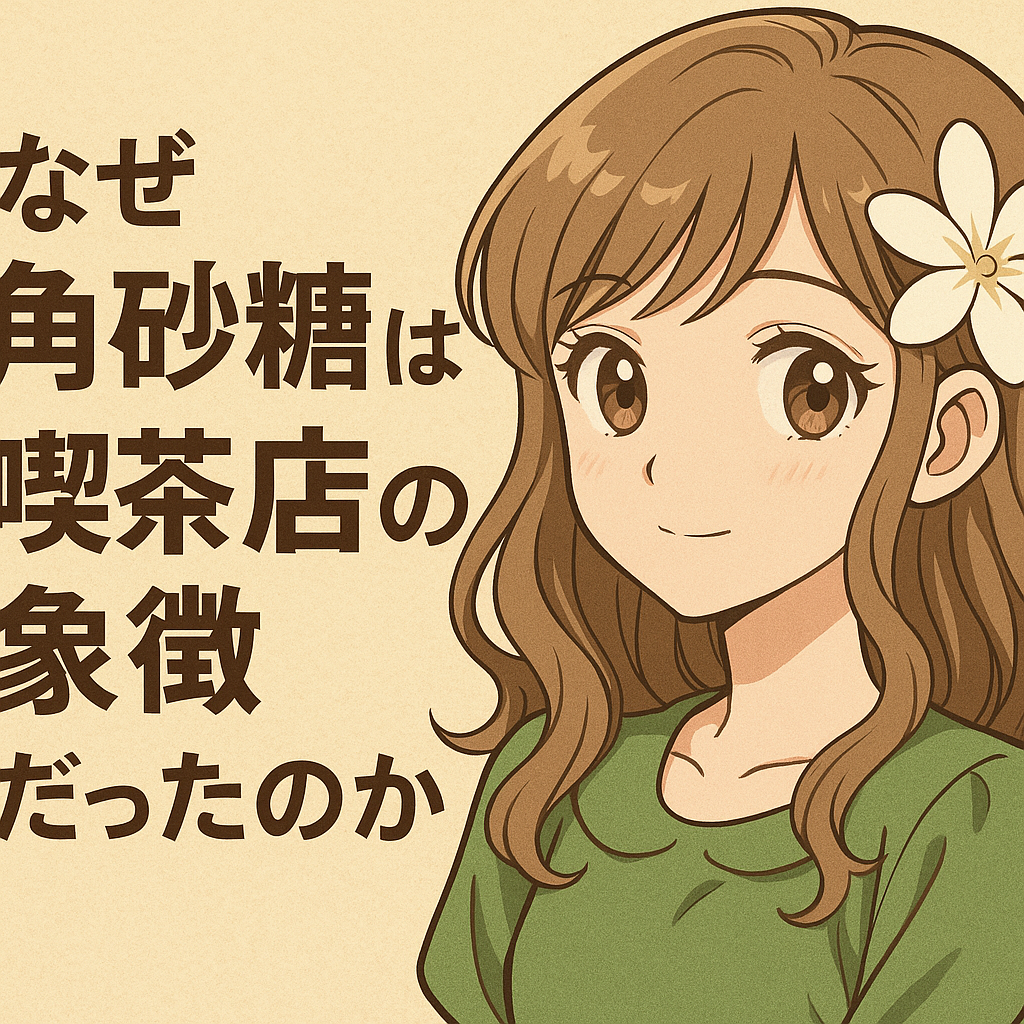
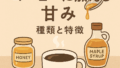
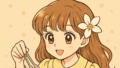
コメント