「レイコー」という言葉を耳にしたことはありますか?
大阪や京都の老舗喫茶店に行くと、今でもたまに飛び交うこの言葉。実はこれ、「冷たいコーヒー」=冷コーヒーの略なんです。
現在では「アイスコーヒー」という呼び方が主流ですが、なぜかつては「レイコー」と呼ばれ、今も一部で愛されているのでしょうか?
この記事では、喫茶店文化の背景と「レイコー」という呼び名の歴史を紐解きます。
☕ 1. 大阪で生まれた喫茶店略語文化
戦後、日本の喫茶店文化は大阪から広まったといわれています。
大阪の喫茶店は、商人の町らしいテンポの良い接客が特徴で、注文の呼び方も自然と短縮されていきました。
例えば…
- レイコー=冷コーヒー(アイスコーヒー)
- レスカ=レモンスカッシュ
- アメ(甘め)=砂糖とミルク入りコーヒー
- ミルティー=ミルクティー
このように、二文字略語で伝える文化が生まれ、常連とマスターの間ではこれが“粋なやりとり”になっていました。
🧊 2. 「レイコー」が生まれた時代背景
「レイコー」が生まれたのは、1960〜70年代の高度経済成長期。
当時、喫茶店は「サラリーマンの憩いの場」「学生の交流の場」として大人気でした。
- 冷たいコーヒーを提供する店が増え、**「冷コーヒー」→「冷コ」→「レイコー」**と略すように。
- 常連客が「レイコーちょうだい!」と注文し、マスターも軽快に返す。そんな関西らしいコミュニケーションが日常でした。
🌏 3. 「アイスコーヒー」が主流になった理由
1980年代になると、全国チェーンのファミレスやカフェが次々と登場します。
メニュー表記は横文字で統一され、**「Iced Coffee(アイスコーヒー)」**が標準呼称に。
さらにコンビニコーヒーが普及した平成以降は、「レイコー」世代以外にとって聞き慣れない言葉となり、徐々に姿を消していきました。
✅ 4. 今でも「レイコー」は通じる?
今では 大阪や京都の昔ながらの喫茶店、または年配のマスターがいるお店に行くと、今も**「レイコー」**が現役で通じます。
ただし若いスタッフや全国チェーン店では「レイコー?」と首をかしげられ、
「あ、アイスコーヒーのことです」と説明することになるかも。
🌟 まとめ – 「レイコー」は喫茶店文化の象徴
- レイコー=大阪発祥の喫茶店略語(冷コーヒー)
- 1960〜70年代の喫茶店ブームで広まり、常連とマスターの合言葉だった
- 今は「アイスコーヒー」が主流だが、昔ながらの喫茶店ではまだ生きている
🍹 もし大阪や京都の老舗喫茶店に行くなら、あえて「レイコーください」と言ってみては?
ちょっと驚いた顔のあとに、マスターの笑顔と「まいど!」が返ってくるかもしれません。

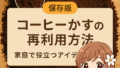
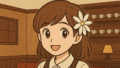
コメント