こんにちは、ティアレです🌺
今日はちょっと特別な旅にご案内します。
舞台は17世紀、帆船が大海を渡っていた時代。灼熱の南洋に降る、一滴の冷たい夢——それが「ダッチコーヒー」の始まりです。
🌍 物語の始まりはインドネシア——ジャワ島
17世紀の東インド。オランダ東インド会社(VOC)の船乗りたちは、赤道直下のインドネシア・ジャワ島に上陸していました。
彼らの目的はただ一つ。
「黄金よりも香り高い豆」——コーヒーです。
当時、コーヒーはイエメンのモカ港からしか手に入らない貴重な飲み物。
そのアラビカ種の苗木を密かに持ち出し、ジャワ島に植えたことから、物語は動き始めました。
🫘 最初のコーヒー豆はアラビカ——モカの記憶を胸に
ジャワ島で最初に実ったのは、イエメン由来のアラビカ種。
焙煎すると、どこかモカのような甘い香りと優しい酸味が漂いました。
けれど、ジャワの昼は灼熱地獄。
火を使ってコーヒーを淹れるなど、もってのほか。
そこで彼らが考え出したのが、水で、ゆっくり、滴らせる抽出法——
そう、これが「ダッチコーヒー(滴下式水出しコーヒー)」のはじまりでした。
🏺 最初のダッチ器具は、理科器具でもガラスでもなかった
当時の器具は、今のようなスタイリッシュなガラス製ドリッパーではありません。
- 氷水を入れた素焼きの壺
- 竹筒や布で作られた滴下装置
- コーヒー粉は布に包んで木枠で支え
- 抽出されたコーヒーは陶器の壺へ静かに滴っていく…
それは実験装置のようでありながら、工芸品のような味わい深さがありました。
何時間もかけて落ちる水の音は、まるで波のしずく。
遠い海を旅した人々の、静かな営みの中で生まれた手仕事でした。
🧊 なぜ冷たくしたのか?それは、生き延びるため
この時代、コーヒーは「温かい飲み物」としての文化をまだ持ちませんでした。
赤道直下の植民地で、加熱せずに飲む工夫は、
日射病、火事、労力を避けるための**「生きる知恵」**でもあったのです。
結果として、その知恵が生んだ「冷たいコーヒー」は、
やがてヨーロッパへ逆輸出される魅惑の嗜好品となっていきました。
💡 ロブスタ種と現代の再発見
時代が下り、19世紀にはロブスタ種(苦味とコクが強い豆)が登場。
それはかつてのアラビカとは違い、タフで、大量生産に向いた品種でした。
このロブスタが、現代のダッチ抽出と出会うことで、
苦味をまろやかにし、チョコのような余韻を生む新たな表現が生まれています。
つまり、**ダッチコーヒーは進化を続ける「古くて新しい芸術」**でもあるのです。
📜 最後に——一滴にこめられた時間の旅
ティアレは思います。
一滴一滴のコーヒーには、
遠い国の風、航海の記憶、そして人々の工夫と祈りが詰まっているって。
現代のガラス器具がきらめく中で、ふと思い出してみてください。
あの一滴は、海を渡った冷たい夢なのかもしれません。
☕ 次回予告:
「氷と風の中の贅沢——日本における水出しコーヒー文化の発展」も予定しています♪
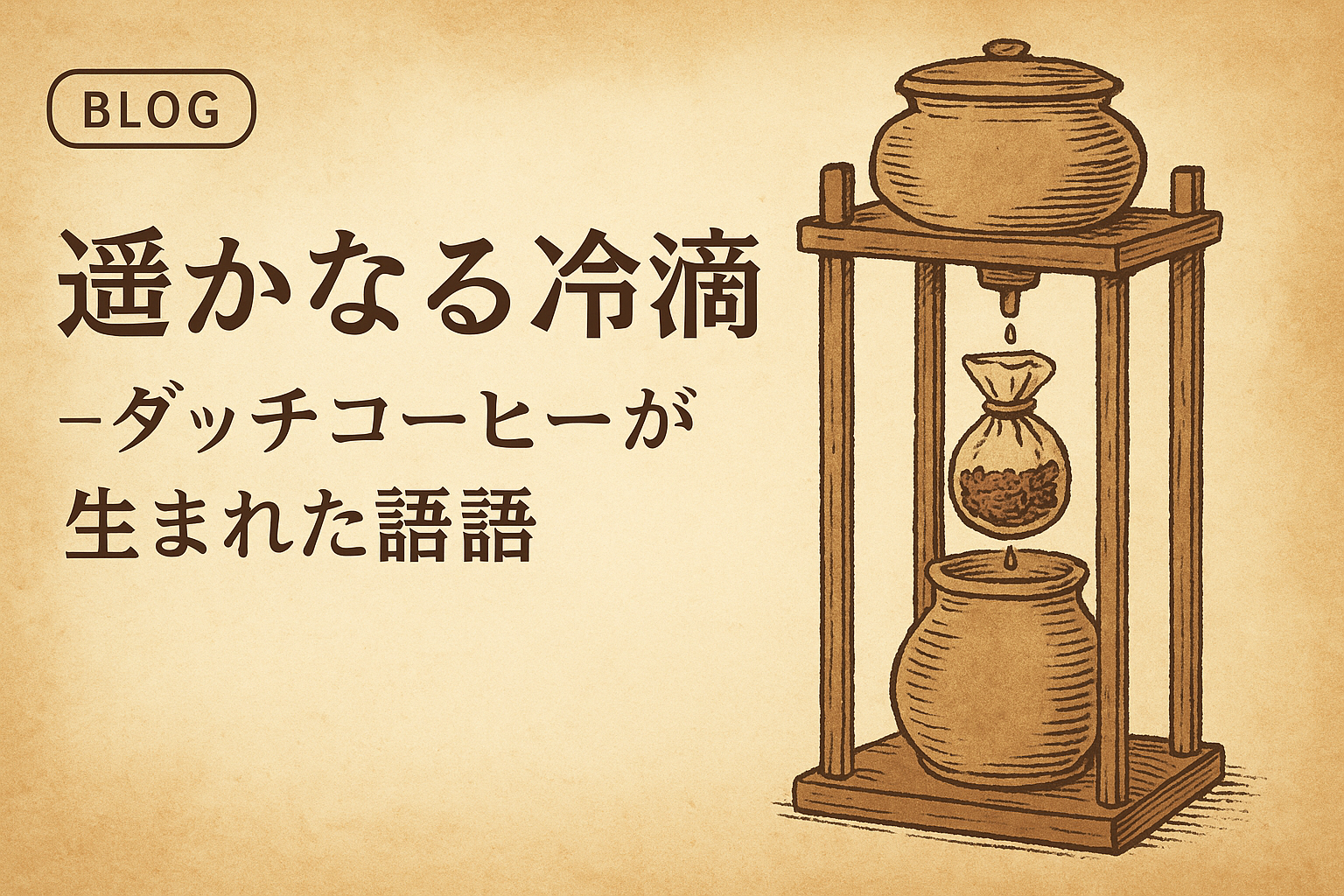






コメント